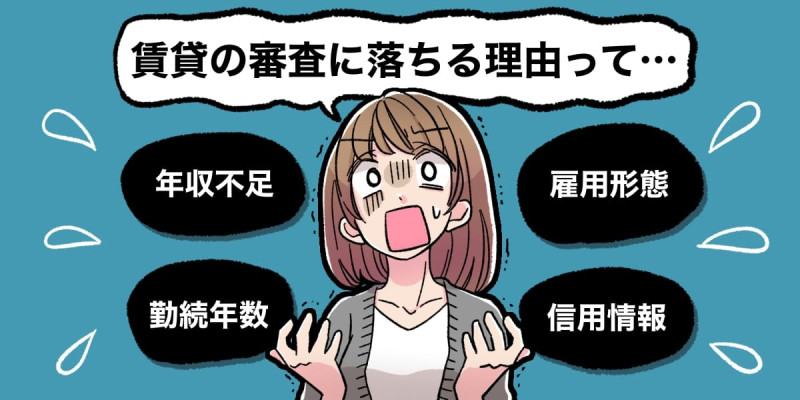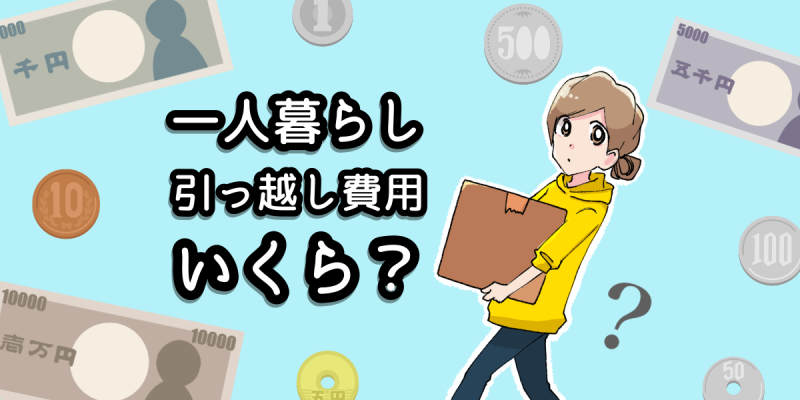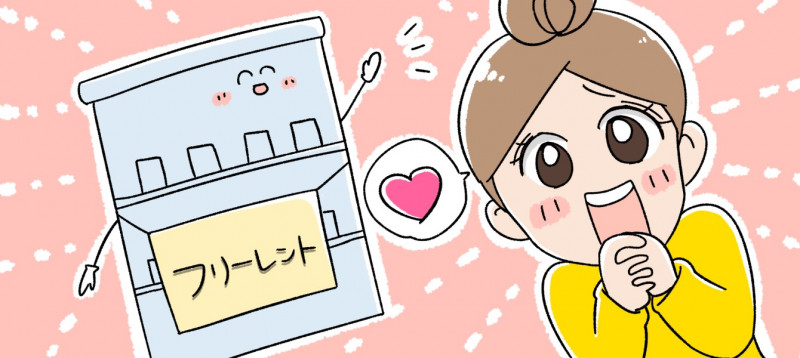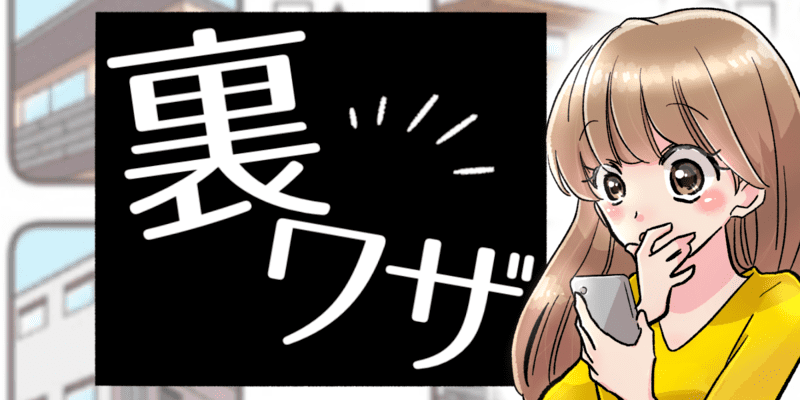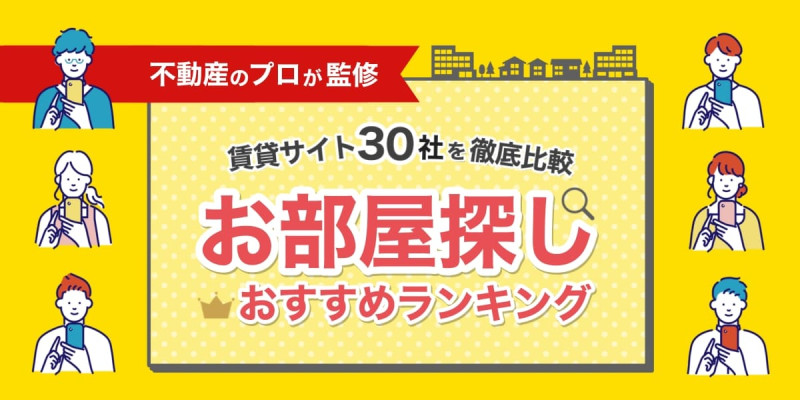「高卒で一人暮らしはきつい?」
「高卒で一人暮らしの家賃目安はいくら?」
高卒後に、地方の大学へ行く人や就職を機に一人暮らしを始める人は大勢います。親に干渉されない、自由度が高い、自立したいなどメリットが沢山あります。
しかし、そもそも高卒で一人暮らしは可能なのか…。お金の問題はどうやって解決すれば良いのかなど、不安に思うことが沢山あります。
当記事では、高卒で一人暮らしがきつい理由や、一人暮らしを始めるまでに必要な費用、毎月の生活費について徹底解説します。節約方法もあるので、ぜひ参考にしてください。
ファイナンシャル・プランナー
宅地建物取引士
日本FP協会認定のFP。お金に関する知識を活かし、一人暮らしからファミリー世帯まで幅広い世帯の生活費を算出しています。宅建士の資格も取得しており、お客様の収入に見合った家賃を提案するなど、生活設計についてのトータルサポートをおこなっています。
高卒で一人暮らしがきついと言われる理由
- ・親の同意が必要と言われるケースが多い
- ・入居審査が通りづらい
- ・高卒の給料が低い
- ・一人暮らしを始める前に大金が必要
- ・家事を一人でこなさないといけない
親の同意が必要と言われるケースが多い
2022年4月から、成人年齢が18歳にかわりました。しかし、賃貸不動産屋では18歳は責任能力に不安が残るため、親の同意が必要と言われるケースが多いです。
もしくは「親と同伴で来店」か「代理契約」を求められます。代理契約とは、代理人が入居者に代わって契約することです。
入居審査が通りづらい
高卒の場合は「社会経験が少ない」「責任能力に不安がある」「収入が低く家賃滞納しそう」と認識されるので、入居審査に通りづらい傾向があります。
入居審査は、大家さんや保証会社が「物件を貸しても大丈夫な人か」「家賃を滞納しないか」を確認するためのものです。申込者側に少しでも不安要素があると不利です。
高卒の給料が低い
| 高卒 | 167,400円 |
|---|---|
| 短大卒 | 183,900円 |
| 大学卒 | 210,200円 |
厚生労働省公表の「学歴別初任給額の推移」データを見てもわかるように、高卒の初任給は最も低いです。
初任給額から「年金」「保険料」「所得税」などが差し引かれます。実際に手元に残るお金は毎月12.5~13万円ほどしかありません。
家賃を考えると、生活費は10万円を切ります。上手にお金をやりくりをしないと、一人暮らしは無理です。
一人暮らしを始める前に大金が必要
一人暮らしを始める前に、70万円前後の大金が必要です。「賃貸の初期費用」「引っ越し費用」「家具家電光熱費」「初月の生活費」分のお金を用意しないといけないからです。
東京の最低賃金で計算した場合、高1の夏ころからアルバイトを始め、毎月2.5万円貯金しなければいけません。足りないときは親にお願いして賄ってもらう必要があります。
家事を一人でこなさないといけない
一人暮らしを開始すると、料理・洗濯・ゴミ出しなど全て自分でこなさないといけません。仕事終わりに家事までこなすとなると、慣れていない内はかなり重労働になります。
面倒になって放置すると、外食で食費がかさんだり、洗濯物やゴミが溜まって汚部屋になってしまいます。
検索で見つからない
お部屋を探します
- 検索で見つからないお部屋探します
- 仲介手数料基本0円
- 上場企業が運営で安心
高卒で一人暮らしをした人の体験談
母子家庭でも母が頑張って高校行かせてくれて高校でバイトして修学旅行も行けた。趣味も楽しんで高卒で金融に就職し一人暮らしを始めた。
デザイン系の仕事が諦めきれなくて
転職して働きながら勉強中。。
母子家庭だから可哀想なんてことはないし、やりたい事やる。
やっぱお金はないけど。笑— かな(@kana1111t) January 13, 2021
高卒すぐ一人暮らし開始して飯食って生きてきたから誰か褒めてほしい、てかこの生活も5年目突入とか笑えない、5年も独りじゃん
— もっくん (@mo52lazydancer) April 12, 2019
高卒で就職して1年半くらいで辞めて、バイトしながら一人暮らししてて全然お金ないけど、こんだけ楽しく生きてるよ。
何が言いたいかって、新社会人のみんな、仕事しんどいかもしれんけど、辞めても案外なんとかなるし、若いうちなら今の時代転職もハードル下がってるから大丈夫だよってこと。— Muto (@____mmt3) May 9, 2019
実はわたしも高卒で一人暮らし始めてから学費も生活費も全部自分で払ってたから少なからずしんどさは分かるんですよね でもあの頃の経験があるからちょっとやそっとじゃへこたれないし努力は報われるって身をもって学んだ
— チッチー (@wiper_tf) April 12, 2022
Twitter上で実際に高卒で一人暮らしを経験した人の声を集めてみました。結果、金銭面できつい・しんどいという声が大半でした。
ただ、お金に関するマイナスな呟きが多い反面、生活自体は慣れればできるという声も多かったです。新卒で一人暮らしを開始してからしばらくは、忍耐力との勝負になりそうです。
高卒が一人暮らしするまでに必要なお金
| 家賃6万円の初期費用例 | |
|---|---|
| 賃貸契約の初期費用 | 270,000~300,000円 |
| 引っ越し料金 | 37,000~82,000円 |
| 家具家電の購入費用 | 100,000~150,000円 |
賃貸の初期費用は家賃の4.5~5ヶ月分
| 相場 | 用語解説 | |
|---|---|---|
| 敷金 | 家賃0.5~1ヶ月分 | あらかじめ預けておくお金で、退去時にお部屋の修繕や原状回復などに使用される。退去時に費用を精算して、残金があれば返金される。 |
| 礼金 | 家賃0.5~1ヶ月分 | お部屋を貸してくれる大家さんへのお礼の意味を込めた費用。敷金とは違い退去時に返金されない。 |
| 前家賃 | 家賃1ヶ月分 | 入居開始する月の翌月分の家賃。事前に前家賃を支払えば、入居した月は翌月分の家賃を請求されない。 |
| 日割り家賃 | 入居日によって変動 | 入居開始日から月末までの家賃を日割り計算した費用。月ごとの日数に合わせて計算する「実日数割」や、月の日数に関係なく30日で計算する「30日割」など、不動産屋によって計算方法が異なる。 |
| 鍵交換費用 | 15,000~20,000円+税 | 前の入居者が利用していた鍵を、新しい入居者が利用する鍵に交換するための費用。ほとんどの物件はセキュリティの関係から交換必須。 |
| 火災保険料 | 15,000~20,000円 | 火事や台風、雷など自然災害で建物・家具に損害を受けた場合に補償してくれる保険料。指定された保険会社に加入することが多く、契約期間は約2年。 |
| 仲介手数料 | 家賃0.5~1ヶ月分+税 | 賃貸契約の仲介をしてくれた不動産屋に支払う手数料。宅地建物取引法で「上限は家賃1ヶ月+税」と決まっていて、それ以上請求されることはない。 |
| 保証会社手数料 | 総賃料の50~100% | 連帯保証人の代わりの役割を果たしてくれる会社を利用するための費用。大家さんに対して、家賃や債務の代位弁済(立替払い)してくれる。 |
| 退去時の クリーニング代 (敷金がないとき) |
30,000~80,000円 | 退去時のクリーニング代を先払いするお金。通常は敷金から充てられるが、敷金なしだと初期費用として払うことが多い。 |
| 相場 | 用語解説 | |
|---|---|---|
| 敷金 | 家賃0.5~1ヶ月分 | あらかじめ預けておくお金で、退去時にお部屋の修繕や原状回復などに使用される。退去時に費用を精算して、残金があれば返金される。 |
| 礼金 | 家賃0.5~1ヶ月分 | お部屋を貸してくれる大家さんへのお礼の意味を込めた費用。敷金とは違い退去時に返金されない。 |
| 前家賃 | 家賃1ヶ月分 | 入居開始する月の翌月分の家賃。事前に前家賃を支払えば、入居した月は翌月分の家賃を請求されない。 |
| 日割り家賃 | 入居日によって変動 | 入居開始日から月末までの家賃を日割り計算した費用。月ごとの日数に合わせて計算する「実日数割」や、月の日数に関係なく30日で計算する「30日割」など、不動産屋によって計算方法が異なる。 |
| 鍵交換費用 | 15,000~20,000円+税 | 前の入居者が利用していた鍵を、新しい入居者が利用する鍵に交換するための費用。ほとんどの物件はセキュリティの関係から交換必須。 |
| 火災保険料 | 15,000~20,000円 | 火事や台風、雷など自然災害で建物・家具に損害を受けた場合に補償してくれる保険料。指定された保険会社に加入することが多く、契約期間は約2年。 |
| 仲介手数料 | 家賃0.5~1ヶ月分+税 | 賃貸契約の仲介をしてくれた不動産屋に支払う手数料。宅地建物取引法で「上限は家賃1ヶ月+税」と決まっていて、それ以上請求されることはない。 |
| 保証会社手数料 | 総賃料の50~100% | 連帯保証人の代わりの役割を果たしてくれる会社を利用するための費用。大家さんに対して、家賃や債務の代位弁済(立替払い)してくれる。 |
| 退去時のクリーニング代 (敷金がないとき) |
30,000~80,000円 | 退去時のクリーニング代を先払いするお金。通常は敷金から充てられるが、敷金なしだと初期費用として払うことが多い。 |
賃貸の初期費用は、一般的に家賃の4.5~5ヶ月分です。家賃5万円なら55.5~25万円、家賃6万円なら27~30万円が目安です。
ただし、敷金礼金の有無やオプションによって初期費用の金額が変動します。申し込み前に不動産屋にお願いして、概算見積もりを出してもらったほうが確実です。
引っ越し費用は一人暮らしで約4~8万円必要
| 荷物が少ない | 荷物が多い | |
|---|---|---|
| ~15km未満 (同一市町村) |
約37,500円 | 約48,900円 |
| ~50km未満 (同一県内) |
約40,000円 | 約51,100円 |
| ~200km未満 (同一地方内) |
約51,000円 | 約59,700円 |
| ~500km未満 (近隣地方) |
約52,100円 | 約75,100円 |
| 500km~ (長距離) |
約59,600円 | 約82,400円 |
引っ越し費用は、移動距離・荷物量によって金額が変わってきますが、目安は4~8万円です。
新卒の一人暮らしなら、実家から持ち出す荷物量が少ないので、定額プランの「引っ越し単身パック」がおすすめです。
家具家電を揃えるのに10~15万円かかる
| 目安金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| シングルベッド | 25,000円 | マットレス・枕などの寝具込み |
| センターテーブル | 5,000円 | - |
| カーテン | 12,000円 | レースカーテン込み・2窓分 |
| 冷蔵庫 | 30,000円 | 150Lタイプ |
| 電子レンジ | 9,000円 | レンジ機能のみ |
| 炊飯器 | 7,000円 | 3合炊き |
| 縦型洗濯機 | 30,000円 | 6kgタイプ |
| 掃除機 | 4,000円 | キャニスタータイプ |
| その他日用品 | 25,000円 | トイレットペーパーなど |
| 合計 | 147,000円 | - |
新卒の一人暮らしは、家具家電を新規購入する人が多いです。生活に必要な物を全て揃えると、10~15万円かかってしまいます。
ベッドは不要、掃除機はクイックルワイパーで代用するなど、最低限のものに絞れば7万円ほどで済みます。
高卒の一人暮らしで毎月かかる生活費目安
一人暮らしの平均生活費は月16万円
| 食費 | 39,069円 |
|---|---|
| 住居 | 23,300円 |
| 水道光熱費 | 13,098円 |
| 家具・家事用品 | 5,487円 |
| 被服及び履物 | 5,047円 |
| 保健医療 | 7,384円 |
| 交通・通信 | 19,303円 |
| 教養娯楽費 | 17,993円 |
| その他の支出 | 31,071円 |
| 消費支出合計 | 161,753円 |
総務省統計局公表の「家計調査2022年度(表番号1)」によると、一人暮らしの1ヶ月の平均生活費は約16万円です。全国平均なので、住んでいる地域や年齢、収入によって差が生まれます。
家賃(住居)が約2.3万円と安い理由は、持ち家や親族からの貸し出し、学生寮やシェアハウスなどが入っているからです。あくまでも、一人暮らししている世帯の集計です。
高卒の初任給を基に生活費をシミュレーション
| 高卒の初任給16.7万円(手取り13万円)の生活費例 | ||
|---|---|---|
| 理想の割合 | 支出目安 | |
| 食費 | 20% | 26,000円 |
| 住居 | 25% | 32,500円 |
| 水道光熱費 | 5% | 6,500円 |
| 家具・家事用品 | 5% | 6,500円 |
| 被服及び履物 | 5% | 6,500円 |
| 保健医療 | 5% | 6,500円 |
| 交通・通信 | 10% | 13,000円 |
| 教養娯楽費 | 15% | 19,500円 |
| その他の支出 | 10% | 13,000円 |
弊社のファイナンシャル・プランナー、岩井さんに新卒の初任給を基に生活費割合を算出して頂きました。
手取り13万円でやりくりをするなら、食費と家賃で手取りの50%未満になるように調整するのがコツです。家賃と食費さえ確保できれば、金欠でもなんとか一人暮らしを継続できます。
 岩井
岩井高卒の一人暮らしは節約必須の生活になる
高卒の一人暮らしは、生活費すべての項目でギリギリの支出です。どうしても調整したい場合は、娯楽費を削るしかありません。徹底的に無駄遣いを省き、日々の節約が重要となります。
食事は職場の賄いを利用するか、3食自炊をするようにしましょう。カップ麺やモヤシは1食が安くなりますが、毎日続けると栄養が足りなくなります。医療費が高くなるので本末転倒です。
家賃も限界まで削ったほうが良いです。このあと、家賃目安やどういうお部屋を探すべきか紹介するので参考にしてください。
初期費用や生活費は家賃を抑えれば余裕が出る
家賃は1度決めるとなかなか下げられないので安いお部屋にすべき
- ・家賃相場が低いエリア
- ・アパートタイプの物件
- ・駅徒歩15分まで緩和
- ・築年数は指定しない
- ・シャワーで済むなら3点ユニットバス
- ・こだわり条件はできれば指定しない
家賃は入居後はなかなか値下げできません。更新のタイミングで交渉はできますが、値下げに値する理由が明確でないと成功しません。
 岩井
岩井高卒の家賃目安は手取りの4分の1
| 手取り額(月収) | 家賃目安 |
|---|---|
| 手取り12万円(月収15万円) | 30,000円 |
| 手取り13万円(月収17万円) | 32,500円 |
| 手取り14万円(月収18万円) | 35,000円 |
| 手取り15万円(月収19万円) | 37,500円 |
| 手取り16万円(月収20万円) | 40,000円 |
高卒の家賃目安は手取りの4分の1です。元々の収入が低いので、家賃にお金をかけすぎると生活費が確保できません。
手取り18万円を超えるようになったら、一般的に言われている家賃目安である「手取りの3分の1」にしても良いです。
安すぎるお部屋は注意が必要
周辺相場より極端に安すぎるお部屋は「築古」「水場が共有」「事故物件」など、住みづらい条件が揃っている可能性があります。不動産屋になぜ安いのかを確認すべきです。
当サイト運営のネット上の不動産屋「イエプラ」なら、来店不要でチャットやLINEからすぐに状況を確認できます。管理会社に直接確認してくれるので、最新情報も教えてもらえます。
夜23時まで営業しているので、受験やバイトが忙しい人でもスキマ時間を活用してお部屋探し可能です!是非試してみてください。
賃貸の初期費用を抑える6つのコツ
- ・引っ越す時期が選べるなら閑散期にする
- ・敷金礼金なしのゼロゼロ物件を探す
- ・連帯保証人のみで契約できるお部屋にする
- ・月末もしくは月初に入居日を設定する
- ・フリーレント物件を選ぶ
- ・不動産屋にAD付き物件を紹介してもらう
引っ越す時期が選べるなら閑散期にする
引っ越す時期が選べるなら、不動産屋の閑散期である4月中旬~8月中旬がおすすめです。
繁忙期に決まらなかったお部屋は、次の繁忙期まで空室が続く可能性があります。大家さんの収入がなくなるので、家賃や管理費を値下げしているケースが多いです。
 岩井
岩井敷金礼金なしのゼロゼロ物件を探す
敷金礼金なしのゼロゼロ物件は、家賃2ヶ月分の費用が浮きます。礼金は100%大家さんの収入なので、借主にとってはメリットがないです。
敷金は、退去費用の預け金です。入居前と入居後、どちらの費用が高くなって良いか考えておきましょう。なお、敷金なしのお部屋は、別途クリーニング費が必要です。
連帯保証人のみで契約できるお部屋にする

保証会社を使わず、連帯保証人を立てるだけで入居できる物件なら、保証会社の利用料分を節約できます。家賃0.5~1ヶ月分ほどの費用を抑えられます。
ただし、保証会社利用が必要な物件は年々増加しています。東京都内では、約7~8割の物件が保証会社必須になっているほどです。
月末もしくは月初に入居日を設定する
日割り家賃は入居日から月末までの計算となるので、月初めに入居するよりも月末に入居した方が「日割り家賃」が安く済みます。
例えば、30日間のうち29日に入居したとしたら29・30日の2日分の日割り家賃で済みます。
 岩井
岩井フリーレント物件を選ぶ
フリーレントとは、大家さんが決めた期間の家賃が無料になるサービスです。期間はバラバラで、最短2週間、最長2ヶ月ほどです。
交渉でフリーレントを付けてもらえることがあるので、申し込み前に不動産屋に相談してみるのもアリです。
不動産屋にAD付き物件を紹介してもらう
AD付き物件とは、大家さんが不動産屋に広告費を支払っているお部屋です。仲介手数料を交渉してもらいやすいです。
 岩井
岩井高卒でもすぐできる生活費節約方法6選
- ・レンジで出来るズボラ料理を始める
- ・1度にたくさん作って冷凍しておく
- ・お茶やコーヒーは家で沸かして持って行く
- ・コンビニの利用を控える
- ・1日ごとや1週間ごとに食費を分ける
- ・外食は格安チェーン店を利用する
レンジで出来るズボラ料理を始める
レンジで出来るズボラ料理を覚えれば、時短になるので光熱費の節約にも繋がります。耐熱タッパさえあれば、カレーやパスタ、チャーハンや煮物など大抵のものを作れます。
大学や仕事から帰ってきて疲れていても、すぐ料理を作れるので自炊が長続きしやすいです。
1度にたくさん作って冷凍しておく
週末など時間がある時に、まとめて料理して冷凍しておきましょう。忙しい時は、温め直すだけで食事を用意できます。
料理をまとめて作ることで、食材ロスも減らせます。キャベツなら、ポトフ・蒸し野菜・コールスローなど使いまわして調理できます。
お茶やコーヒーは家で沸かして持って行く
お茶やコーヒーは家で沸かして持って行けば、500mlで数10円ほどで済みます。ペットボトルを購入した場合は、100~200円かかるのでもったいないです。
コンビニの利用を控える
コンビニ商品は、定価で販売しています。スーパーや薬局で食品を買うより割高なので利用を控えたほうが良いです。1品数十円の差でも、塵も積もれば山となります。
1日ごとや1週間ごとに食費を分ける
食費は使い過ぎ防止のために、1日ごともしくは1週間ごとにお金を分けておいておくと良いです。使って良い分のみを持ち歩けば、強制的に無駄遣いを防げます。
外食は格安チェーン店を利用する
外食は「はなまるうどん」「吉野家」「マクドナルド」「サイゼリヤ」など、大手格安チェーンがおすすめです。1食あたり500円ほどで済みます。
そもそも高卒で一人暮らしをするメリットとは?
高卒で一人暮らしをする最大のメリットは「親に干渉されないので自由が増える」「責任能力が身につく」ことです。
休日に昼過ぎまで寝ていても怒られませんし、友人や恋人を気兼ねなく呼べます。住む場所を選べるので、通勤通学時間の短縮もできます。
親がいないので、全て自己責任となります。時間の管理やお金の管理、公共の手続きなども全て自分でおこなうので責任能力が自然と身につきます。
 岩井
岩井高卒で一人暮らしする際にあるよくある質問
高卒で一人暮らしするならいつからがベスト?
引っ越す時期が選べるなら、高卒後1年経ってからがベストです。
理由は「一人暮らしするための費用を貯められる」「仕事に慣れてきたので環境を変えても平気」だからです。
高卒すぐに一人暮らしをすると、仕事も私生活も環境が変わるので体調やメンタルを崩す人が多いです。仕事に慣れてきてからのほうが安心です。
高卒で一人暮らしは貯金できる?
月の手取りが18万円未満なら貯金は諦めたほうが良いです。
家賃を差し引いた生活でいっぱいいっぱいになるからです。どうしても貯金をしたいなら、500円や千円貯金から始めましょう。
高卒フリーターでも一人暮らし可能?
高卒フリーターでも一人暮らし可能ですがきついです。
フリーターで月の手取り13万円を稼ぐなら、東京で月153時間、岩手で月192時間バイトしなければいけません。正社員より、お金のやりくりが厳しくなります。
高卒で一人暮らしで仕送りなしはきつい?
仕送りなしで一人暮らしはきついですが、できないことはありません。
高卒で一人暮らしで仕送りなしは、節約は必須の生活です。賃貸の初期費用と毎月の生活費で、徹底的に無駄を省きましょう。
東京で高卒一人暮らしするなら家賃はいくら?
東京で高卒一人暮らしするなら家賃は5万円ほどかかります。
東京は、日本一物価が高い街です。一人暮らし向けのワンルームですら、平均家賃が7~8万円です。住む場所や駅徒歩・築年数など条件は妥協しましょう。
東京都内にこだわりが無いなら、千葉や埼玉など家賃相場が低いエリアでお部屋を探すと良いです。家賃4万円ほどのお部屋が見つかります。
当サイト運営の「イエプラ」なら、わざわざお店に行かなくてもLINEで希望を伝えてお部屋を探せます!
さらに、イエプラは仲介手数料が基本0円です。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。
家賃によっては10万円以上も安くなるので、浮いたお金で新生活の家具家電を揃えられます。費用を抑えて引っ越したい人は、ぜひ利用してみてください。